
雨は、傘をさしても肩口から入ってくる。駅前のアーケードを抜けたところで、私はビニール傘を畳み、濡れた手の甲で前髪を押さえた。髪の水気は頬に落ち、ひんやりとした筋が顎の先へ流れていく。
ビルの自動ドアが開くと、外の湿度が一瞬だけ切り離されたみたいに、冷房の乾いた空気が肌の表面を撫でた。濡れた部分だけが際立つ。世界はいつも、濡れているところを見つけるのが上手い。
エレベーターを待つ間、壁の鏡に映る自分の胸元を見る。名札が、まだ半分濡れている。
「受付 佐伯」
透明のケースの中で紙が少し波打っていて、文字が弱々しく見えた。私は指でケースを押さえたが、もう乾く気配はない。
フロアに着くと、奥の休憩室から笑い声がした。早番の女の子が、スマホを見せ合っている。私が扉を開けると、笑いは潮が引くみたいに小さくなり、代わりに空気がじわりと重くなった。
誰も悪くない、という種類の重さ。私の胸元の名札みたいに、湿り気を含んでいる。
「おはよ」
声は普通に出た。自分の声が、こんな日に限って普通に出るのが少し腹立たしい。
私はロッカーを開け、タオルを取り出し、名札のケースを拭いた。拭いても紙の波打ちは直らない。私はケースを外して、紙だけを持ち上げた。指先が濡れた紙に触れると、文字が少し滲んだ気がした。
その日、店にかかってくる電話は少なかった。雨の日は、いつも少ない。
私は受付カウンターの奥で、フォームに打ち込む。名前、希望時間、指名、オプション。入力欄に沿って文字を置くと、世界が整理されていくように錯覚できる。整っていれば安心、というのは、たぶんこの仕事だけじゃない。
ふと、来客用の傘立てを見る。黒い長傘が一本、妙にきちんと立っている。柄に、擦れた銀色のシールが貼ってあった。
「記名」
昔の学校の備品みたいな、まじめな文字。傘は忘れられたのだろうか。持ち主は、気づかないまま帰ったのか。気づいても戻れない事情があったのか。
傘は何も言わない。濡れたまま、ここに居るだけだ。
昼過ぎ、電話が鳴る。
「はい、佐伯です」
相手は女の子だった。声が、息を詰めたガラスみたいに薄い。
「……面接って、どんな感じですか」
問いの形は普通でも、中身が普通じゃないことは、受話器越しに伝わってくる。
「すごく軽い感じですよ。お茶飲みながら、希望を聞く感じで」
私は言い慣れた言葉を選んだ。選んだ言葉は、いつも少しだけ嘘を含む。嘘というより、濃度を薄めた本当だ。
「履歴書いらないですか」
「いらないです」
「……怖くないですか」
「怖くないです」
私は答えながら、傘立ての一本の傘を見た。怖い、という言葉は雨粒みたいに、誰にでも落ちる。落ち方が違うだけだ。
「今日、行ってもいいですか」
「もちろん」
私は、声の向こうの湿り気に対して、乾いた布を差し出すみたいに「もちろん」を置いた。
電話を切ったあと、名札に目がいった。滲んだ文字。私は自分の名前を見て、なぜか、私自身が少し薄くなっていく気がした。
佐伯、という人が、誰かの不安の受け皿になっていくほど、紙の繊維みたいに毛羽立って、輪郭を失っていく。
面接の時間まで、私は休憩室で紙コップのコーヒーを飲んだ。苦い。苦さが、舌に残って、口の中が現実になる。
テーブルの端に、スタッフ用の備品一覧が置かれている。消耗品の在庫、洗剤、タオル、ティッシュ。どれも、なくなる前に補充する。なくなってからだと遅い。
私はふと思った。人の気持ちは、在庫管理ができない。足りなくなる前に補充できない。足りなくなったことに気づいてから、慌てて買いに行く。行けない人もいる。買う場所がわからない人もいる。
ドアがノックされ、面接の女の子が入ってきた。背が低く、髪の毛がまだ雨の匂いを持っていた。
「こんにちは」
「こんにちは。座って」
私は紙コップの水を渡した。手が少し震えた。私の手だ。私の手が震えるのは、たぶん、彼女が若いからでも可愛いからでもない。
彼女が、昔の私に似ているからだ。似ている、というのは、顔じゃなくて、湿り気の方向が。
「名前、聞いてもいい?」
「……莉子です」
言い方が、躓くみたいだった。言葉の端が欠けている。
「今日は雨だったね」
「はい……」
「濡れなかった?」
「ちょっと」
彼女は笑おうとしたが、笑いは途中で止まった。私は、その止まり方を見て、胸の奥が少し痛んだ。止まる笑い。止めざるを得ない笑い。
面接は、いつも通り進んだ。希望の出勤、どれくらい稼ぎたいか、身バレ対策、送迎。私は口から言葉を取り出し、彼女の前に並べた。
でも、言葉を並べても、雨が止むわけじゃない。雨は外に降っているし、彼女の中にも降っている。
「不安なこと、あります?」
そう聞くと、莉子は紙コップの縁を指でなぞった。
「……わたし、向いてないかもしれなくて」
「何が?」
「全部です」
全部、という言葉は軽いのに重い。箱に入らない重さ。
私は頷き、しばらく沈黙した。沈黙は、乾いた布みたいに見えるときがある。実際は濡れているのに。
「向いてるとか向いてないとか、最初はみんなわからないよ」
私は言いながら、名札を指で押さえた。滲んだ文字が、さっきより薄い。
「うち、無理させない。やれる範囲でやればいい」
そう言うと、莉子は少しだけ肩の力を抜いた。
「……ほんとですか」
「ほんと」
ほんと、という言葉の頼りなさを私は知っている。だから、私は続けた。
「最初は見学だけでもいいし、体験だけでもいいし。嫌ならやめていい。やめていいって言える場所が、いちばん安心だと思う」
莉子はその言葉を、舌で確かめるみたいに目を閉じた。
「やめていい……」
繰り返した声が、少しだけ湿っていた。
面接のあと、彼女は「お願いします」と言った。
その言葉は、誰かに何かを預けるときの、薄い布みたいな重さがあった。私はその布を受け取り、落とさないように両手で持った。
責任、というより、祈りに近い重さ。
夕方、雨が上がった。空は、濡れたアスファルトをまだ手放していない。
私は受付カウンターの下で、古い名札の紙を探し出した。予備の紙。
新しい紙に「佐伯」と書き、透明ケースに入れた。文字がくっきりと立つ。私はそれを胸に付け直した。
鏡を見ると、私の輪郭が少し戻っていた。
でも、戻ったのは文字の濃さだけかもしれない、とも思った。人は、今日一日で簡単に戻れたりしない。
閉店間際、私は傘立ての一本の傘を手に取った。柄のシールに「記名」とある。
私は受付票の裏にペンで書き足した。
「忘れ物:黒い傘(記名シールあり)」
記名。名前。名前は、濡れても滲んでも、誰かを呼ぶためにある。
そして、呼ばれることで、こちらも少しだけ救われる。
外に出ると、街の空気が少し軽かった。雨上がりの匂いは、昔の傷を思い出させる。でも同時に、乾く前の短い時間にだけある、正直な匂いでもある。
私はビルの前で立ち止まり、胸元の名札を指で触れた。紙は乾いている。文字は滲んでいない。
それでも、私は知っている。明日また雨が降れば、また濡れる。
濡れたら、拭けばいい。滲んだら、書き直せばいい。
書き直すことは、敗北じゃない。呼ばれるための、ささやかな作業だ。
私は、アーケードの端で空を見上げた。雲の切れ目に、薄い青が覗いている。
その青は、濡れた名札の上にも、きっといつか落ちる。
私は小さく息を吐き、声に出さずに自分の名前を呼んだ。
佐伯、と。
呼ばれた私が、少しだけここに戻ってくる。
そして、誰かの「全部です」という重さを、今日より少し軽く持てる気がした。



 検討中
検討中 マイページ
マイページ

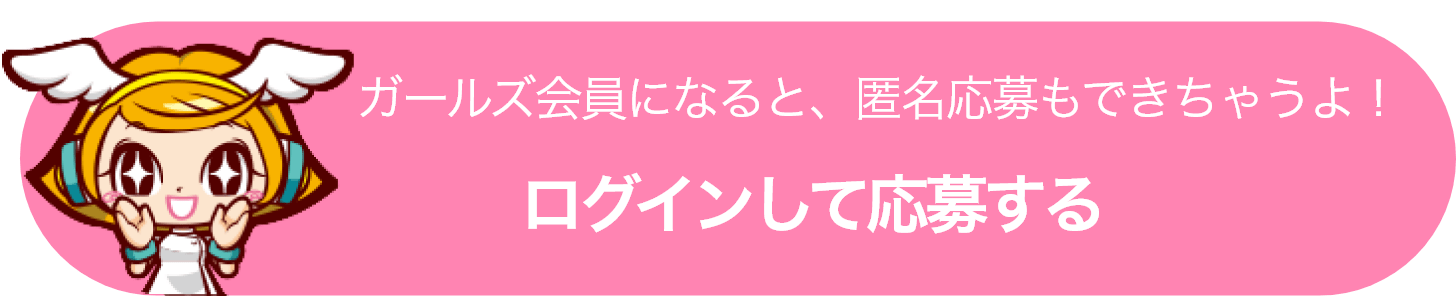


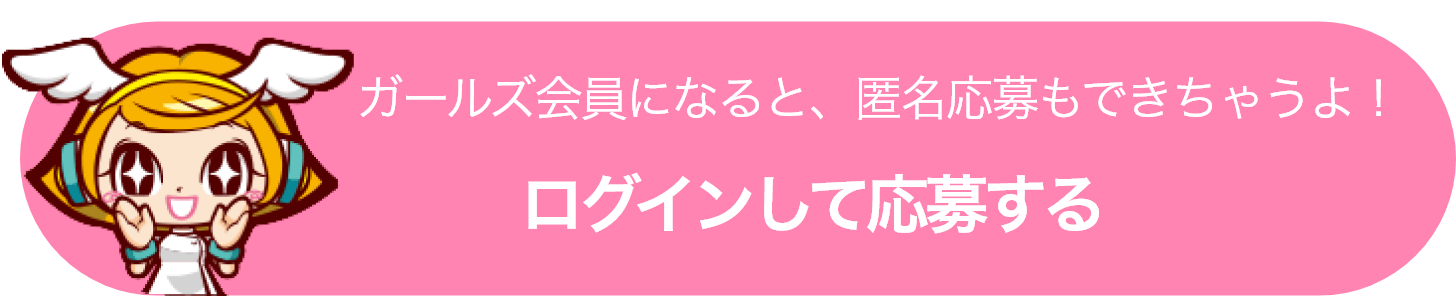





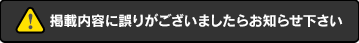
 ページのトップへ
ページのトップへ